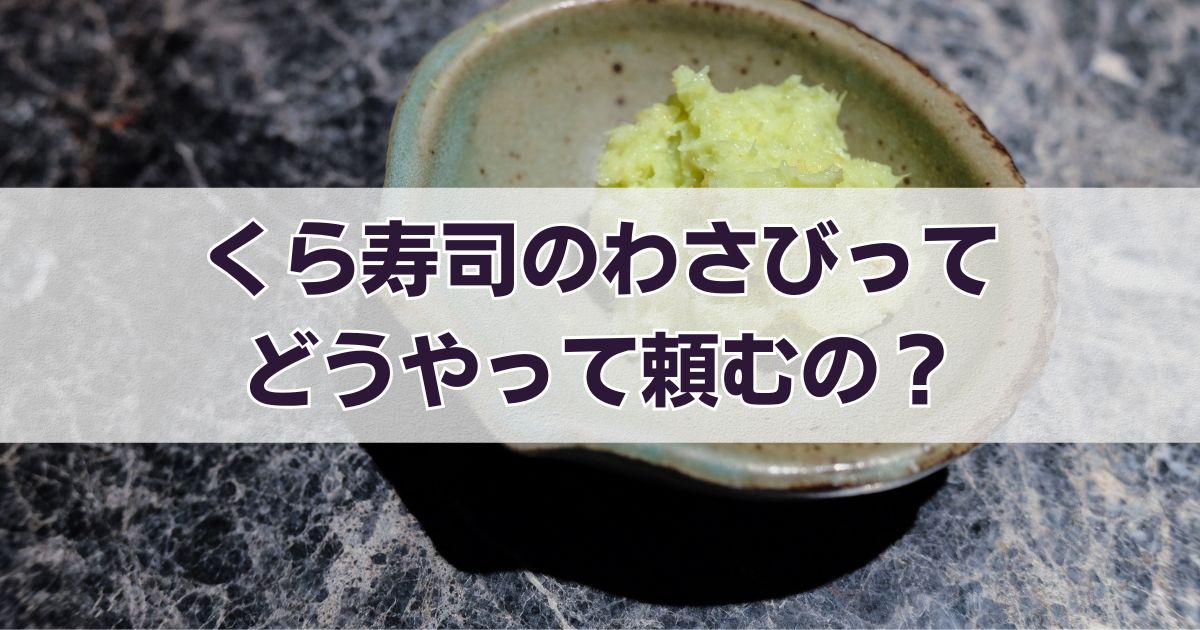おすしは、日本のたべものの中でも、子どもから大人までたくさんの人にあいされている人気の料理です。
とくに回転ずしは、たんじゅんなシステムと、手ごろなねだんが大きなみりょくで、毎週のように食べに行く人も少なくありません。
そんな回転ずしの中でも、くら寿司は、しぜん派をうたう全国チェーンとして知られ、メニューやサービスがとても工夫されています。
けれども、さいきんではたいていの回転ずし店で「わさびぬき」が標準になっており、くら寿司でも多くのにぎりずしが、最初からわさびが入っていないかたちで提供されています。
とはいえ、「やっぱりおすしにはわさびがかかせない」と感じている人も少なくありません。
はじめてくら寿司を利用する人にとっては、「わさびはどこにあるの?」「どうすれば頼めるの?」というギモンがうかぶこともあるでしょう。
そこでこの記事では、くら寿司でわさびを手に入れる方法や、店員さんへの依頼の仕方、さらにはわさびの品質や特徴についても、くわしくごしょうかいしていきます。
このガイドをよめば、次にくら寿司に行くとき、わさびをもっとじょうずに、そしておいしく楽しめるようになりますよ。
なぜいま「サビ抜き」が当たり前になったのか?
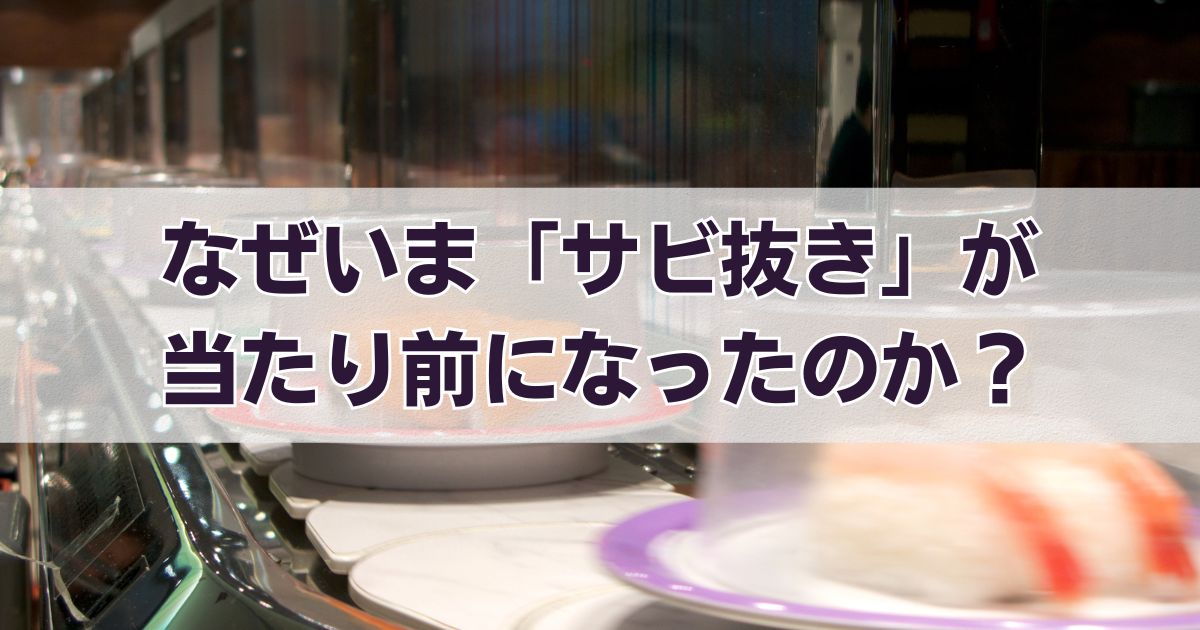
むかしのおすしといえば、シャリとネタのあいだにわさびがぬられているのがふつうでした。
とくに江戸前ずしでは、わさびの風味がネタのうま味をひきたてる大切な役目をもっていました。
ところが、近年ではわさびを入れずに提供する「サビ抜き」のスタイルがあたりまえになっています。
そのいちばんの理由は、食のスタイルやすうせいが時代とともに変わってきたからです。
子どもにもやさしいおすしを目ざして
回転ずしはファミリーでの来店がとても多く、ちいさなお子さまもたくさんたのしんでいます。
けれども、わさびのツンとしたからさは、子どもにはつよすぎて、食べにくいことがあります。
そこで、はじめからわさびを入れないことで、子どもでもすなおにおすしを食べられるようにしたのです。
鮮度をまもるための工夫はすでにじゅうぶん
江戸時代、わさびは魚のにおいをおさえたり、ばいきんのはんしょくをふせぐために使われていました。
ところが、いまでは冷蔵や保冷のぎじゅつが大きく進歩しており、わさびを使わなくても、食べものの安全がしっかりたもたれています。
このため、くら寿司では、必要な人だけがあとから自分でわさびを加えるスタイルをとっています。
くら寿司のテーブルにはわさびがある?
「わさびはどこにあるの?」と気になる人も多いですが、じつはくら寿司では、各テーブルにわさびの容器がちゃんと用意されています。
このわさびは小さなスプーンで取り出すタイプで、使う分だけ自由にすくって自分のおすしにのせることができます。
衛生面は大丈夫?
共用のわさび容器というと、気になるのが「他の人と同じスプーンを使うのはちょっと不安……」という声です。
でも、くら寿司では「クリーンテーブル制度」をしっかりと行っていて、すべてのテーブルはつねにきれいにふき取り、容器もときどき交換されています。
そのため、安心してわさびを使えるようになっています。
わさびの質にもこだわるくら寿司
ただ提供するだけでなく、くら寿司ではわさびそのものの品質にもとてもこだわっています。
使っているのは、「清水(しみず)」とよばれる水でそだった「本わさび」で、からさの中にもうま味や香りがしっかりあるのが特徴です。
本わさびってなに?
本わさびとは、日本の山のなかのきれいな川の近くで育つ、しょくぶつの根っこの部分です。
おろし金ですって使うことで、さわやかな香りとピリっとしたしぜんなからさが感じられます。
とくに、すりたての本わさびは風味がとても強く、おすしやさしみを引き立てる調味料として最適です。
なぜ「あとから加える方式」なの?
すでにおすしにわさびが入っていると、人によっては「からすぎる」と感じることもあります。
くら寿司では、おきゃくさんが自分の好みに合わせてわさびの量を決められるように、最初は「サビ抜き」で出すようにしているのです。
このやり方なら、わさびが苦手な人も安心して食べられますし、わさびが好きな人もたっぷり使えて満足できますね。
実は「小袋わさび」もあるってホント?
さいきん、「くら寿司では、びんじゃなくて小袋タイプのわさびがもらえるらしいよ」というウワサが広がっています。
実際に、「共用のびんはちょっと気になるから、個包装のわさびをください」と言えば、対応してくれる店舗もあるようです。
ただし、これはあくまでもお店によってちがうため、すべてのくら寿司で必ずもらえるわけではありません。
もし気になる方は、店員さんに聞いてみるのがいちばん確実です。
わさびの使い方まとめ
さいごに、くら寿司でのわさびの使い方について、かんたんにおさらいしておきましょう。
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| わさびの置き場所 | テーブルの上にある小さな容器。小さなスプーンで取り出す。 |
| 衛生への配慮 | クリーンテーブル制度により、テーブルや容器の交換・消毒がされている。 |
| 小袋タイプの存在 | 店舗によっては、店員さんにお願いすれば小袋タイプももらえる場合がある。 |
| 自由な調整が可能 | わさびの量は自分の好みに合わせて自由に加えることができる。 |
くら寿司では、こうした配慮をとおして、だれもがじぶんのペースでたのしめるおすし体験を提供しています。
【まとめ】くら寿司でわさびも一緒に楽しもう!
この記事では、くら寿司でのわさびのありかや、使い方、そしてわさびにこめられたこだわりについてご紹介してきました。
「サビ抜き」がふつうになっても、わさびの風味やからさは、やっぱりおすしに欠かせないと感じる方もいるはずです。
くら寿司では、その気持ちにちゃんとこたえるように、わさびを自由に使えるスタイルをとっています。
これからくら寿司を訪れるときには、わさびにもすこし注目してみてくださいね。
わさびの使い方ひとつで、おすしの味がぐんとひきたちますよ。