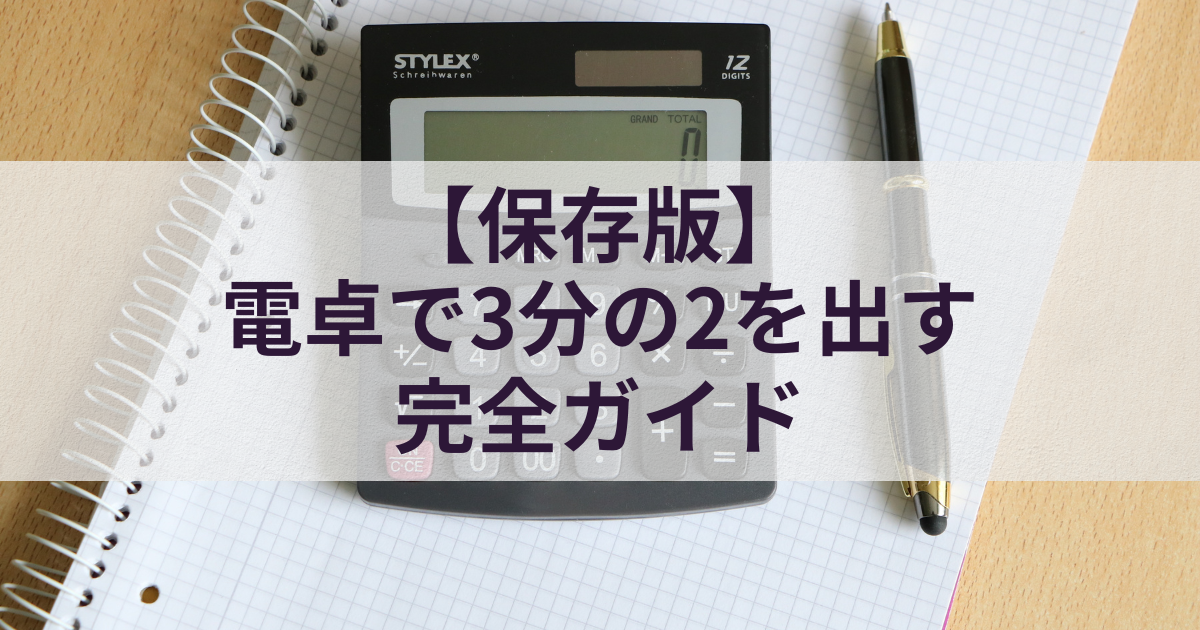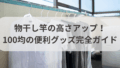3分の2を計算してください」と言われて、ちょっと困ったことはありませんか?
学校では習ったはずなのに、大人になってから使おうとすると忘れてしまっていることもよくあります。
とくに、電卓を使って分数を計算しようとすると、「どうやって入力したらいいの?」と悩んでしまう方も多いです。
この記事では、そんな「3分の2」の計算について、いちからやさしく説明していきます。
まずは、3分の2がどんな意味を持っているのかを確認しながら、基本の計算方法を覚えましょう。
さらに、電卓での具体的な入力方法や、電卓が使えないときの手計算のコツも紹介します。
そして、日常生活や仕事の場面でどう使うかという実例も紹介します。
わかりやすく説明するので、算数が苦手な方でも安心してくださいね。
3分の2とはどういうこと?基礎から理解しよう
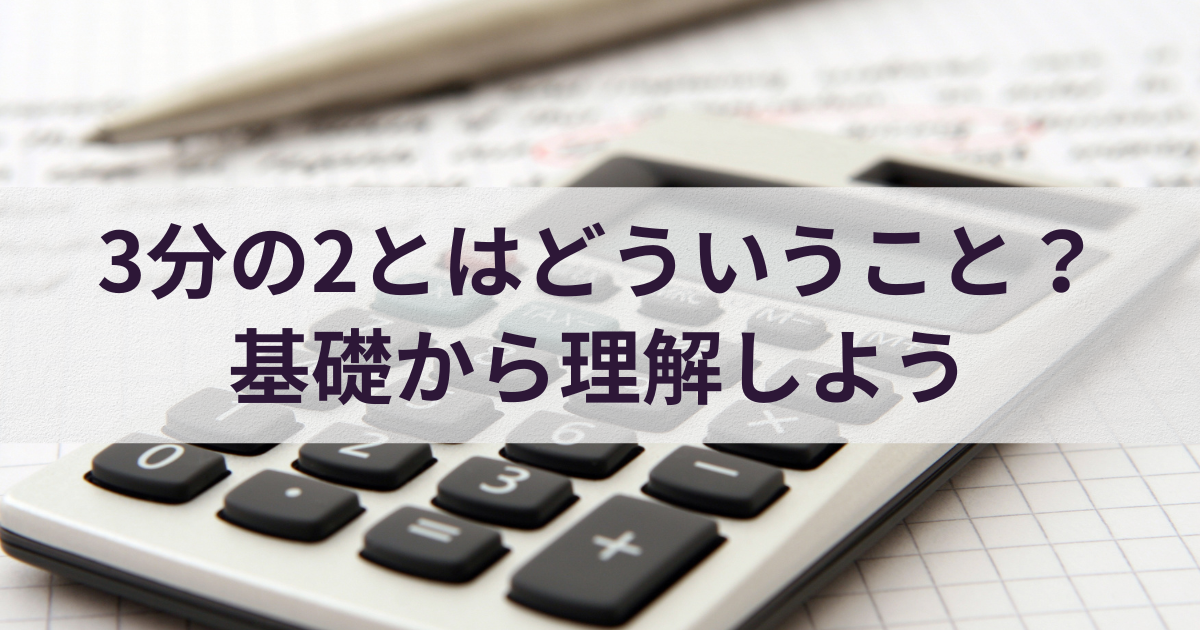
「3分の2」という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、どんな意味があるのか知っていますか?
これは、何かを3つに分けたときの、2つ分を表している数です。
たとえば、ホールケーキを3人で分けて、そのうち2つ分を食べたなら、それが「3分の2」です。
分数は、物の量や比率を表すときにとても便利です。
そして、「3分の2」のような形は、割合や割引などにも応用できます。
この基本的な考え方がわかると、いろいろな場面で使えるようになりますよ。
「2/3」の持つ意味とは?
「3分の2」は、数字で書くと「2/3(にぶんのさん)」と読みます。
これは、「3つに分けたもののうち、2つ分を取る」という意味です。
たとえば、ピザを3等分して、そのうちの2切れを食べると、「3分の2食べた」ことになります。
また、合計が100人いる中で、その3分の2が女子だったら、66人くらいが女子になります。
割合や比率の表現にもよく使われる分数です。
分数から小数・パーセントへの変換方法
「3分の2」を小数に直すには、「2 ÷ 3」をすればOKです。
この計算の答えは「0.666…」と続くので、だいたい「0.67」と覚えると便利です。
そして、この小数に100をかけると、パーセントに変わります。
つまり、「0.67 × 100 = 67」となるので、「3分の2」はだいたい「66.7%」となります。
分数・小数・割合の変換表
| 表記 | 値 |
|---|---|
| 分数表記 | 2/3 |
| 小数表記 | 約0.67 |
| パーセント | 約66.7% |
このように、分数から小数、そしてパーセントへと変えることができるんですね。
買い物やテストの点数の計算にもとても役立ちます。
電卓で3分の2を出すやり方とは?

電卓があれば、「3分の2」の計算もとてもかんたんになります。
ただし、ボタンの押す順番を間違えると、違った答えが出てしまいます。
ここでは、正しい式とその入力方法を、わかりやすく説明します。
基本の計算式「元の数 × 2 ÷ 3」の意味
「3分の2」を求めるには、「元の数 × 2 ÷ 3」という式を使います。
たとえば、「12万円の3分の2」を出すときは、「120000 × 2 ÷ 3」と入力します。
なぜこの順番かというと、先に掛け算をしたほうが、小数が出にくく、正確な計算ができるからです。
計算は、できるだけ整数で処理したほうがミスが少なくなります。
電卓での具体的な入力手順
実際に電卓で計算してみましょう。
たとえば、120,000円の3分の2を出す場合、以下のように入力します。
手順:「120000 × 2 ÷ 3 =」
この順番で入力すると、答えは「80000」と表示されます。
これで、3分の2の金額がわかります。
どんな金額でも、この方法でスムーズに計算できます。
よくある入力ミスと注意点
よくある間違いの一つに、「÷3 × 2」と逆の順番で計算してしまうことがあります。
この順番だと、小数が出てきてしまい、思った通りの結果にならないことがあります。
計算の順序は「元の数 × 2 ÷ 3」と覚えておくと安心です。
また、電卓で数字を入力するときは、押し間違いにも気をつけましょう。
手計算で3分の2を求める方法
電卓がないときでも、「3分の2」は手で計算できます。
ここでは、2つの簡単な方法をご紹介します。
割り算と掛け算で段階的に求める方法
1つ目は、3等分してから2倍する方法です。
たとえば、120,000円を3分の2にしたいときは、まず「120000 ÷ 3」で「40000」と出します。
その「40000 × 2」で、「80000」が答えになります。
この方法は、暗算でもやりやすいです。
分数をそのまま掛け算で使う方法
もう一つの方法は、「元の数 × 2/3」という式を使うことです。
120,000円の場合、「120000 × 2 ÷ 3」で「80000」となります。
分数の掛け算に慣れている人には、こちらのほうが速いかもしれません。
実際に役立つ「3分の2」の計算場面
「3分の2」の計算は、意外と身の回りのいろいろなところで使われています。
ここでは、具体的なシーンを紹介します。
割引価格や分担金の計算に活用!
たとえば、30%引きの商品を買うとき、残りの支払額は3分の2になります。
定価6000円の商品なら、「6000 × 2 ÷ 3 = 4000円」で計算できます。
また、3人でごはんを食べた後、2人分の合計を知りたいときも、「全体の金額 × 2 ÷ 3」で求められます。
学校の授業や試験でも使われる!
学校の算数でも、「3分の2」はよく登場します。
たとえば、長方形の面積が90平方センチのとき、「90 × 2 ÷ 3 = 60」で、3分の2の面積が出ます。
割合の問題や、グラフ、図形の問題にもよく出てくるので、覚えておくとテストにも強くなります。
ビジネスでの費用分担や進捗管理にも
社会に出ると、仕事の中でも「3分の2」を使うことがあります。
たとえば、「このプロジェクトは3分の2まで終わっている」とか、「費用の3分の2を会社が出して、残りは自分で払う」といったときです。
正しく計算できれば、仕事もスムーズに進みます。
「3分の2」の計算を早く正確にするためのコツ
慣れてくると、「3分の2」の計算はすぐにできるようになります。
ここでは、覚えておくと便利なコツを紹介します。
暗記の工夫と考え方のコツ
「3分の2」を暗記するコツは、「まず3で割ってから2倍する」と覚えることです。
たとえば、60,000円なら「60000 ÷ 3 = 20000」、「20000 × 2 = 40000」で答えが出ます。
よく使う金額の3分の2をいくつか覚えておくと、もっと速く計算できます。
よくある間違いを防ぐ方法
多くの人がやってしまうのが、「÷3 × 2」の順番でやってしまうことです。
正しい答えが出ないことがあるので、必ず「×2 ÷3」の順でやりましょう。
また、電卓を使うときも、ゆっくり確認しながら押すようにしましょう。
まとめ
「3分の2」の計算は、わかってしまえばとても簡単です。
電卓でも手計算でも、「元の数 × 2 ÷ 3」の式を覚えておけば、いつでも使えます。
日常生活から学校の勉強、仕事の現場まで、たくさんの場面で役に立ちます。
ぜひ、この記事を参考に、3分の2の計算方法をしっかり身につけてくださいね。